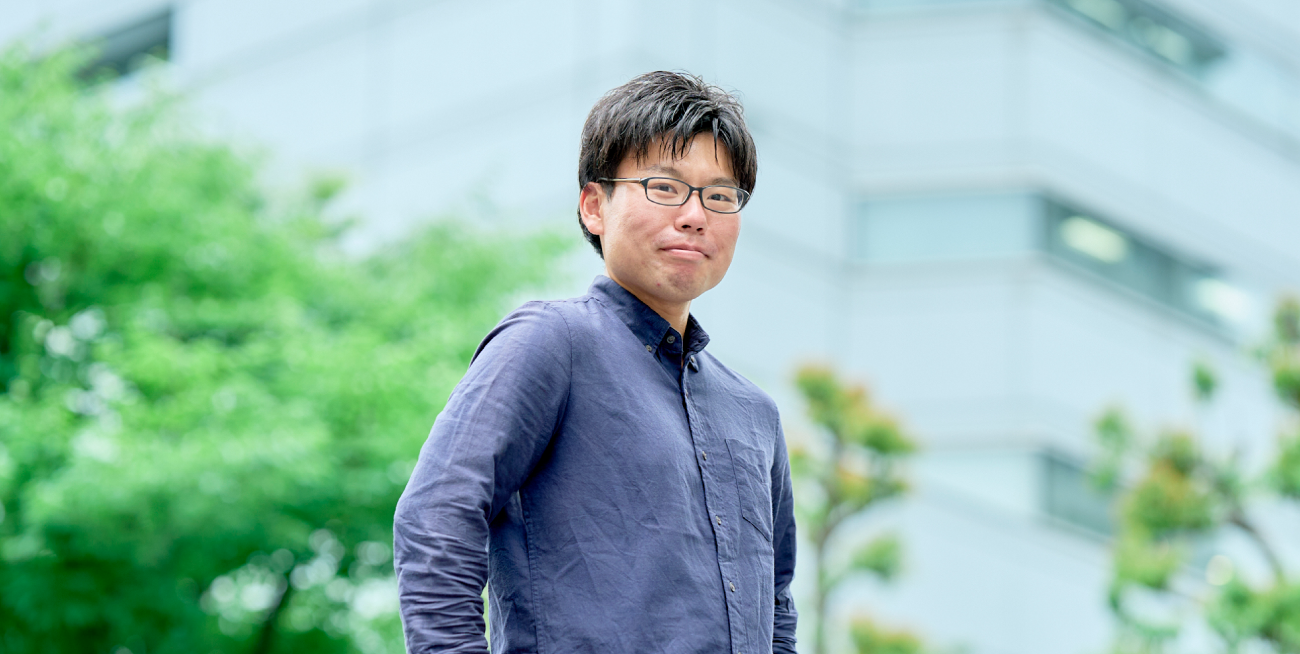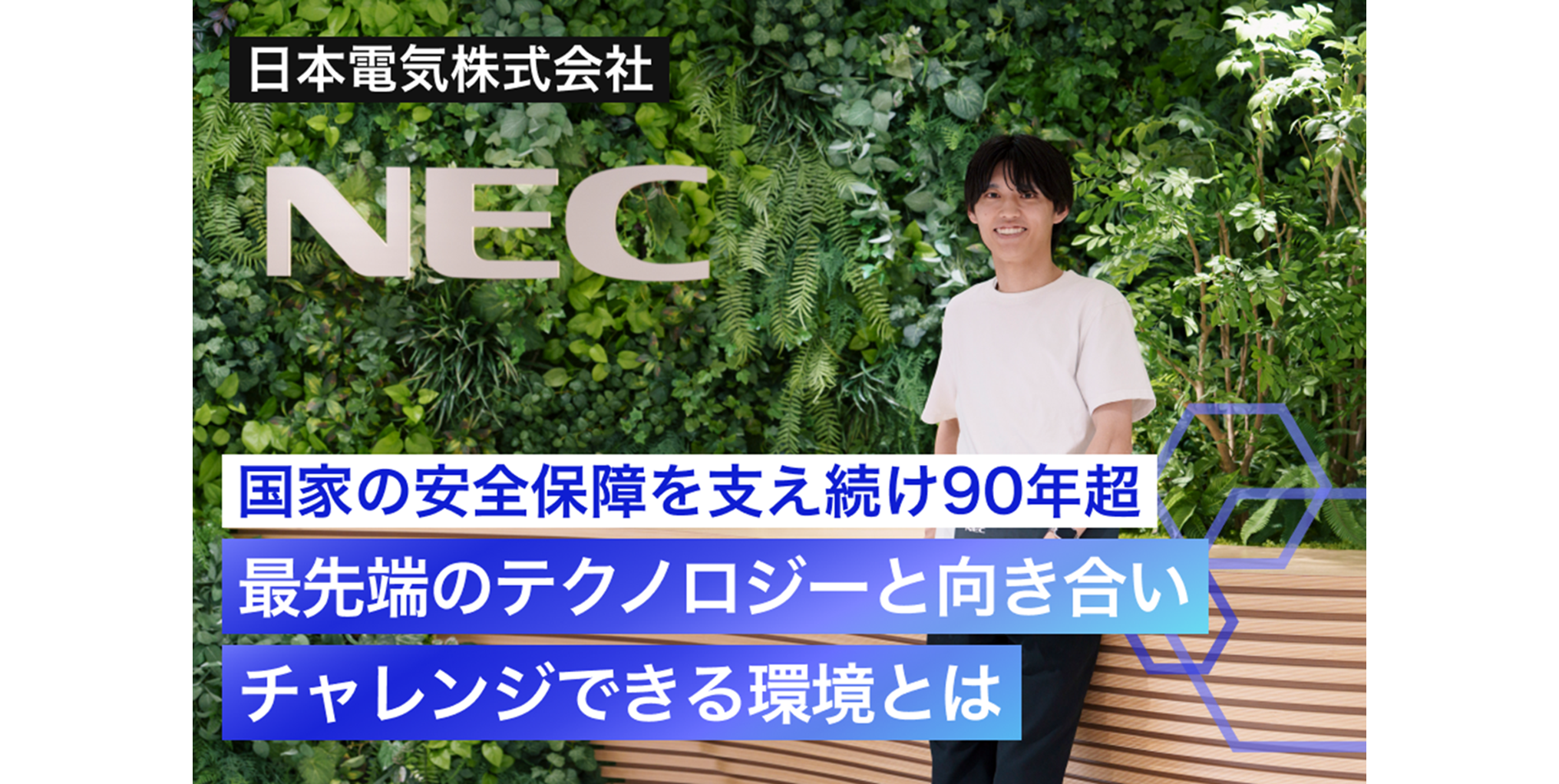海洋システム事業部門で海底ケーブルの生産管理を担当しているYukie K.。子育てと仕事を両立できる環境を求め、2021年にNECへキャリア入社しました。インフラをつくる仕事がしたいという長年の夢をかなえ、今年4月にはマネージャーに昇格したYukieが、「子どもに誇れる仕事」の魅力を語ります。
数年がかりで完成する海底ケーブル。プロジェクトの動向を踏まえ、生産計画を立案。

私は海洋システム事業部門の海洋SCM・QMS統括部に所属しています。統括部には大きく生産管理と品質保証の2つのグループがあり、私は生産管理のグループで生産計画の立案を担当しています。具体的には、プロジェクトに応じて中継器や端局装置といった製品の生産スケジュールを立案し、在庫管理などを行うのが主な業務です。
業務のフローとしては、まず営業から今後のプロジェクトの動向や新設・増設案件などの情報をキャッチすることから始まります。その後、案件の進捗状況や受注確度、仕様の詳細などを確認し、工場の稼働状況を踏まえて生産スケジュールを立案していきます。
そして受注確度が高まると生産開始のタイミングを判断し、工場へ発注をかけます。さらに製造・検収を経て、現地工事のタイミングに合わせて輸送できるよう、輸送チームへ引き渡すまでが一連の流れです。
海底ケーブルの仕様や設計は、プロジェクトによって変わります。途中で大きな変更が生じる場合もあるため、生産の平準化が難しい点がこの仕事の特徴です。また大型案件が続けば稼働率が上がり、受注までに時間がかかる案件が多い場合は稼働率が低下してしまうこともあります。
こうした課題に対応するため、プロジェクトマネージャーと密接に連携して調整を行っています。たとえば、稼働率が高い時期にはお客様にスケジュールの調整をお願いしたり、稼働率が低い時期には前倒しで生産できる製品がないかを検討したりしています。
調整は難しいですが、生産管理を通じて社会インフラを支えられることがやりがいです。各分野のプロフェッショナルが専門知識を持ち寄り、細かい生産調整を重ね、数年後にようやく社会インフラを支える海底ケーブルが完成する。その壮大なプロセスに携われることに、日々喜びを感じています。
とくに、社内のコミュニケーションツールを通じてお客様への引き渡しが完了したなどの報告を受けると、無事にプロジェクトが完了したという大きな達成感を味わいます。
働きやすい環境を求めてNECへ。やりたい仕事に出会い、充実した教育制度のもとで成長。

前職では、外資系の建設機械メーカーに14年ほど勤務していました。最初の数年間はマーケティング部門で関連会社の経理や人事制度などの業務支援を担当し、アメリカ本社への駐在も経験しました。
もともとインフラをつくる仕事がしたいという想いがあったため、ものづくりの現場を体験するべく生産管理部門に異動しました。仕事はとても充実していたのですが、子育ての関係で一度仕事を離れることになります。当時は子どもが病気がちで、仕事との両立が難しくなってしまったのです。
その後、時間の経過とともに子どもの体調も安定してきたので、この状況ならやりたい仕事ができると考え、転職活動を始めました。
次の職場を探す際に重視したのは、子育てのサポート体制が充実していること、そして子育てをしているかどうかにかかわらず正当な評価をしてくれる会社であることです。また、今までとは異なる新たなチャレンジがしたいという想いもありました。
こうした希望に合致していたのが、NECです。面接時に子育てとの両立について相談したところ、入社前に会社の制度について説明する機会をわざわざ設けてくださって、人事部門の方が積極的にサポートしてくれたのです。実際に入社してからも、とても働きやすい環境だと実感しています。
最初に配属されたのはパソコンの販促部門だったのですが、インフラをつくる仕事に携わりたいという想いは変わらず持ち続けていました。そんな折、通年で実施されている社内公募制度「NEC Growth Careers」で、海底ケーブル事業の生産管理職について募集しているのを見つけました。まさに私がやりたいと思っていた仕事だと思い、応募して海洋システム事業部門へ異動しました。
異動して印象的だったのが、サポート体制がとても充実していたことです。海洋システム事業部門は、異動やキャリア採用などで転入してくる人材が多い部署のため、教育制度がしっかりと整備されています。各部署の業務説明や光通信の基礎など、初心者向けに数カ月かけて丁寧に教えてもらえたため、専門知識を着実に身につけることができました。
さらにメンター制度もあり、転入者同士の交流会も定期的に開催されます。ほかにも先輩社員が転入後の経験にもとづき、後輩へアドバイスしてくれる機会もあるなど、非常にサポートが手厚く、仲間がいるという安心感の中で新たな業務に取り組むことができました。
キャリア入社の視点で業務改善を推進。ステップアップを重ね、マネージャーに昇格。

キャリア入社としての視点を活かし、これまでいくつかの業務改善に取り組んできました。その1つが、Excelによる生産管理表の作成を効率化したことです。当時、Excelの転記作業が多く発生していたため、この業務プロセスを改善したいと考えました。
検討を重ねた結果、システムからデータを取り込んで処理できるよう、Accessへの移行を実施。マクロ処理を導入し、ボタン1つでデータを取り込める仕組みを構築しました。以前は1件ずつシステムを開いて数字を転記していたため、チームメンバーからも作業が楽になったとうれしい声をかけてもらいました。現在もさらなる効率化をめざし、業務の改善を検討しています。
また、部門内の大規模なタスクフォースに参加したことも、私にとって新たな挑戦です。業務改善のため、原価管理と発注において使用しているシステムの見直しに取り組みました。そしてより詳細な予実管理ができるシステムへの移行を実現し、今年5月から本番稼働を開始しています。
このタスクフォースにメンバーとして選ばれたのは、1on1で業務改善に取り組みたいという想いを伝えたことがきっかけでした。海洋システム事業部門では、キャリア入社ならではの視点や経験が浅いからこその気づきを、積極的に取り入れようとする風土があります。
会議などでも社歴や役職を気にせず質問したり発言したりでき、それをしっかりと受け止めてもらえます。そのため疑問を放置することがなく、業務に対する理解を1歩ずつ深めることができました。その結果、自分にできる仕事が増えていき、タスクフォースにアサインされるなど新たな挑戦の機会が得られました。このような好循環により、業務の範囲がどんどん広がり、着実にステップアップしているのを実感しています。
そして今年4月には、マネージャーへの昇格も果たすことができました。昨年度から管理職登用が自己推薦制となり、自ら手を挙げて試験を受けられるようになりました。私は管理職を希望していたので応募し、試験に合格。マネージャーになり、今まで以上に組織のために新たな提案ができるようになったと感じています。
手を挙げる人には次々とチャンスがくる。やりたい仕事ができる環境で、次のステップへ。

異動時の面接で覚えているのが、事業部長から「なんでもやりたいことに取り組んでください」と言われたことです。実際に働く中で、本当にやりたいことに挑戦できていると感じます。手を挙げる人にはどんどんチャンスを与えてくれる環境です。
そして海洋システム事業部門だけでなく、全社的に社員がまじめで優しいこともNECの魅力だと思います。私が「こういうことに挑戦したい」と話すと、それを実現するために周囲の仲間がサポートしてくれます。
そしてもう1つ、私がNECの魅力だと感じているのが、安定性と革新性を両立していることです。大企業であるため石橋をたたいて物事を進める堅実さがある一方、新しいことに挑戦する意欲にあふれ、社員からは斬新なアイデアが次々と出てきます。それは長い歴史がありながら、「変わり続けることを変えない」組織ならではのおもしろさだと感じています。
NECへ入社して5年目を迎えましたが、今後は全体最適のための提案ができるようになることが目標です。これまでは海底ケーブルに関する専門知識を増やし、目の前の業務をこなすことに精いっぱいだったところがありました。
しかしマネージャーとなった今は、全体を俯瞰する視点が養われてきたと感じています。これからは組織横断でさまざまな人を巻き込みながら、全体最適のための取り組みを推進していきたいと思います。
子どものことがきっかけでNECへ転職しましたが、異動を経てインフラをつくる仕事に携わることができ、あきらめずに夢を追い続けて良かったと心から思っています。子どもに「お母さんは海底ケーブルをつくる仕事をしているんだよ。海底ケーブルがあるから、世界中の人たちがインターネットで通信できるんだよ」と説明すると、とても喜んで褒めてくれるので、私自身も誇らしい気持ちになります。
私と同じように、インフラをつくりたいという情熱を持っている方が海洋システム事業部門に参加してくれるのを期待しています。NECにはさまざまな可能性があり、新たなことに取り組めるチャンスが多くあります。入社してからでもやりたい仕事に出会えるので、ぜひ幅広いフィールドで活躍してほしいと思います。
※ 記載内容は2025年5月時点のものです