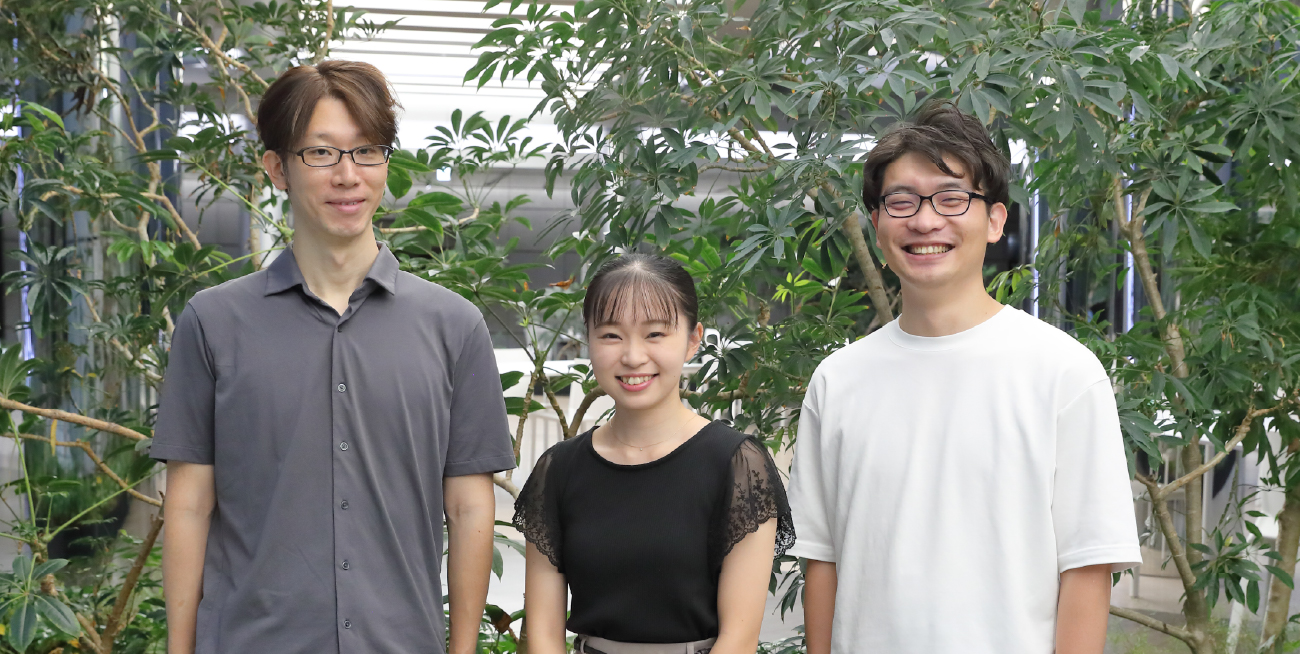中央省庁向けのシステム開発を通じ、安全な暮らしや公共秩序の維持に貢献する第一官庁システム開発統括部。国民の利便性を向上する、中央省庁向けの大型プロジェクトを担うグループにて、マネージャ―を務めるYusuke S.、キャリア入社のHaruka W.、新卒入社のAyano M.が、仕事にかける想いを語ります。
NECの技術力で、行政サービスを高度化。多くの国民に関わる大規模システムを開発

日本電気株式会社(以下、NEC)の第一官庁システム開発統括部に所属する3人。現在、行政サービスを高度化する中央省庁向けの大規模なプロジェクトに取り組んでいます。
Yusuke S.:このプロジェクトは、最大300人のメンバーが関わり2年がかりで進めてきました。2025年のサービスインに向けて、現在は最終調整を行っている段階です。その中で私は、プロジェクトマネージャー(PM)の補佐を務めるPMグループの一員として、各工程における課題の解決やお客様との調整などを担当しています。
Haruka W.:私は昨年9月にキャリア入社し、このプロジェクトへ参加しました。最初は教育チームに所属し、システムの変更点を反映したマニュアルの作成や、システムの変更点に関するお客様向けの研修などを担当しました。その後は納品するシステムに問題がないか確認することを目的とした、立会検査の準備と実施を行ってきました。
Ayano M.:私は今年4月に新卒入社し、7月に本配属されました。それから現在まで、プロジェクトのメンバーとしてシステムの開発研修に携わっています。他にもHaruka W.さんが担当している立会検査のサポートや、プロジェクトの進捗会議における議事録作成、ベンダー間の接続試験の立会などの業務を担当してきました。
セキュリティや品質において、高度な水準を満たすことが求められる中央省庁向けのシステム。これまで他の官公庁向けのシステム開発を担当してきたYusukeは、国民や社会の安全・安心を守るシステムだからこそ、より一層品質が重要だと話します。
Yusuke S.:私たちが開発しているシステムの先にいるのは、多くの国民の皆様です。社会的影響力が大きいからこそ、NECならではの技術力や公共領域のシステム開発で培ったノウハウを活かし、細部まで徹底して品質を追求しています。
HarukaもYusukeと同様に、品質を何より重視していると話します。
Haruka W.:NECに入社する以前から品質第一で開発に取り組んできましたが、膨大なエンドユーザーに影響を与える今回のプロジェクトは、改めて品質の重要性を実感させられます。
それと同時に、法律の施行日など動かせないスケジュールにも対応しなければなりません。品質を確保しながらプロジェクトを迅速に進めていくためにも、すぐ行動に移すことを意識しています。緊張感のある業務ですが、チームの風通しが良く、関係部署がみんな協力的なので仕事が進めやすいと感じます。
本配属になってからまだ日が浅いAyanoも、チームの雰囲気が良いためコミュニケーションが取りやすいと話します。
Ayano M.:高度な専門知識やスキルを持ちながらも、気さくで話しやすい先輩方ばかりです。向上心を絶やさない先輩の姿に刺激を受け、私自身も資格取得の勉強に取り組み、今年度はAWS認定クラウドプラクティショナーを取得しました。
現在は応用情報技術者試験に向けて勉強中です。少しでも先輩方に追いつけるよう、依頼された仕事はすぐに対応したり、会議に参加して議事録を作成してプロジェクトの理解を深めたりと、自分にできることを積み重ねて成長につなげています。
NECだからできる仕事を。多様なバックグラウンドを活かし、難易度の高い業務に挑戦

チームのムードメーカーであるYusuke。NECへは2008年に新卒入社しました。
Yusuke S.:NECに興味を持ったのは、当時ベストセラーとなった折り畳み式携帯電話がきっかけでした。そこから幅広い事業を展開していることを知り、その中でもBtoC向けの事業に携わりたいと考え、スマートフォンやパソコンなどのソフトウェア開発職としてNECへ入社しました。
BtoCの領域を選んだのは、お客様と直接関わる仕事がしたいという想いがあったからです。しかし実際にはお客様のフィードバックをダイレクトに活かせる機会はあまり得られませんでした。お客様との関係性を築きながら、NECの技術力や幅広い事業フィールドを活かして社会の役に立つ仕事がしたい。そう考え、公共領域のシステムエンジニアとして新たなキャリアをスタートしました。
現在の部署ではお客様と密にコミュニケーションを取りながらプロジェクトが進められるため、やりたい仕事が実現できていると感じます。
一方、2024年9月にNECへキャリア入社したHaruka。前職では北海道のメーカー系SIerでシステム開発を担当していました。
Haruka W.:主にWebサービスのシステム開発を行っていました。前職に不満はなかったものの、地元の神奈川に戻る機会があり転職することを決めました。その中でNECを選んだのは、よりプロジェクトの方向性を決めるような大きな意思決定ができるプライムベンダーで働きたいと考えたからです。これまで携わったことがない公共領域に新たに挑戦できることや、NECの社風が自分に合っていると感じたことも決め手となり、NECに入社しました。
前職とNECでは、品質向上のアプローチに違いがあるとHarukaは話します。
Haruka W.:前職では、素早くバージョンアップし顧客からのフィードバックをもとに品質を向上するという価値観がありましたが、NECでは上流工程で徹底的に品質をつくり込んでいます。スピード感を保ちながら品質をいかに向上させるかについては、プロジェクト責任者とフラットに議論できる機会がよくあり、学ぶことがとても多いです。そうした上位者との対話からも、品質にこだわり抜く姿勢を強く感じています。
2024年4月に新卒入社したAyano。大学3年生の時に参加したハッカソンがきっかけでNECを選びました。
Ayano M.:生体認証の技術を使ったシステム開発に挑戦するハッカソンだったのですが、データの照合方法などがとても興味深く、生体認証技術のおもしろさに魅了されました。それを機にNECについていろいろ調べていたところ、米国国立標準技術研究所(NIST)のベンチマークテストにおいて、指紋認証・顔認証・虹彩認証の3つの生体認証技術で精度世界第1位の評価を獲得していることを知りました。
NECへの入社を決めたのは、そうした技術力に加え、ハッカソンを通じて組織風土に魅力を感じたからです。ハッカソンでフィードバックをもらう際、私の技術に関してだけでなく、「反対意見を言う際に、チームの雰囲気に配慮しながら柔らかく伝えられている」と人間性も見ていただけたことが印象的で、NECで働きたいと思いました。
お客様からの信頼を得るために。自らコミュニケーションを取り、関係性を築く

2年がかりで進めてきた今回の大型プロジェクト。その開始にあたり別の部門から異動することになったYusukeは、まずチームづくりから取り組みました。
Yusuke S.:私が期待されていた役割は、前の部門の良い点を取り入れながら改善すべき点を変えるということです。最初に私が感じた課題は、積極的に意見を言うメンバーが少ないということでした。そこで、朝会を行うことを決め、異動の翌日には実行に移しました。朝会を通じ、各リーダーやメンバーの考えを共有できる場をつくりたいと考えたからです。
プロジェクトの規模が大きいので、働く場所もそれぞれ異なり、お互いのことをよく知らないところからのスタートとなります。そのため、まずはコミュニケーションが取りやすい環境をつくることから始めました。
プロジェクトの途中から参画することになったHarukaとAyano。当時の心境をこう振り返ります。
Haruka W.:入社前に国民向けのあるシステムを利用したのですが、そのシステムを手がけていたのが、NECだったと後から知って驚きました。というのも、使い勝手が良かったので1人のユーザーとしてそのフィードバックを送っていたからです。私もこんなふうに身近に使ってもらえるシステム開発に携わりたいと考えていたので、プロジェクトに参加するのがすごく楽しみでした。
Ayano M.:ニュース番組で取り上げられるぐらい注目度が高く、プロジェクトの規模がいかに大きいかを実感して最初は少し不安でした。でも直属の上司が、「どんなことでもわからないことがあればいつでも質問して」と声をかけてくださり、会議後も毎回不明点がないかを確認してくれたので安心しました。また、対面だけでなく社内チャットでも気軽に質問できる環境があり、誰もが親切に答えてくれるので仕事が覚えやすいと感じます。
Haruka W.とAyano M.という新たなメンバーと共に、プロジェクトに取り組んできたYusuke S.。お客様とコミュニケーションを取る上で、とくに意識していたことがあると言います。
Yusuke S.:お客様とより良いシステムを開発するために、何よりも信頼を得ることを意識しました。最初は気軽にご要望をお話しいただけなかったため、まず取り組んだのが自分からコミュケーションの機会をつくることです。メールよりも電話での連絡を心がけ、自分のグループ以外の会議にも可能な限り出席しました。その中で専門的な内容をお客様によりわかりやすくお伝えするなど、何かあれば頼れる存在として認識してもらえるように努めました。
入社前からプロジェクトへの参加を心待ちにしていたHaruka。実際の開発にあたっては、さまざまな苦労があったと振り返ります。
Haruka W.:もっとも苦労しているのは、お客様の業務を理解することです。システムの規模が大きく業務の幅がとにかく広いため、いまだに理解しきれていない業務があります。自分で勉強をしながらも、気になる点や疑問点があればすぐに有識者に確認しています。
時にはお客様に素直にお伝えし、直接教えていただくこともあります。わからないこと、あいまいなことをそのままにしないことが大切だと考えています。技術も業務も引き続き勉強し、お客様に喜んでいただけるシステムを開発していきたいです。
Ayano M.:私もHarukaさんと同じで、業務理解は今も努力が必要だと感じます。また、会議に出席していて感じたのは、他のベンダー企業と連携を図ることの難しさです。関係者が多いため、それぞれの事情を考慮した上で進行する必要があると学びました。上司にもどうすれば円滑に進められるかを積極的に質問し、理解を深めるようにしています。
チームでやり遂げる喜びを原動力に。プライムベンダーとして社会に貢献し続ける

間もなくサービスインを迎える中央省庁向けの大型システム。大規模なプロジェクトだからこそ、得られる達成感ややりがいがあると3人は話します。
Yusuke S.:最大の山場はサービスインですが、各開発工程の完了といった節目だけでなく、解決が難しい課題を解消できた時などたくさんの達成感を感じています。プロジェクトに関わるメンバーが多い分、意思決定のプロセスも多く、時にはグループ内で出した結論を変更せざるを得ない場面もありました。
それはすべて、NECとしての品質に一切妥協しないためです。みんなで意見を出し合い、最終的に同じ方向をめざして走り抜く。そうしてチームで一丸となって何かを成し遂げられることが、何よりのやりがいにつながっています。
Haruka W.:私は教育チームで研修の講師を務め、無事に終えられた時に大きな達成感を感じました。全国から集まっていただいた、130人以上のお客様を前に講義を行うのはかなりのプレッシャーでしたが、チームで準備をした成果が発揮できてとてもうれしかったです。
また、立会検査の準備と実施も印象に残っています。失敗が絶対に許されない仕事なので、Ayanoさんやプロフェッショナルな多くの仲間にサポートしてもらいながら懸命に取り組みました。大変でしたが、プライムベンダーだからこその貴重な経験ができたと感じています。間もなく自分が携わったシステムがリリースされますが、社会で実際に役立てられている様子を見られる喜びも、NECならではだと思います。
Ayano M.:私はまだ1年目で学ぶことが多いため、小さなことでもできるようになるとやりがいを感じます。たとえばコードが書けるようになったり、設計書が書けるようになったりと、社会人になって毎日できることが増えていくのがとてもうれしいです。
Harukaさんと一緒に検査の対応をした時も、仕事を任せてもらえる喜びがあり、それを自分なりに全うできたという達成感がありました。そうした小さな積み重ねを大切に取り組むことで、着実に成長できているのを感じます。
それぞれのやりがいを大切にしながら、3人は次の目標に向かって挑戦を続けていきます。
Yusuke S.:今回のプロジェクトではPMの補佐を担いましたが、次は自分が責任を持つ立場として、プロジェクトの成功につながる意思決定ができるようになりたいと考えています。2年前にこの部署に異動してきて以来、システムを通じてお客様の役に立ちたいという想いが一層強くなっているので、チーム一丸となってさらに貢献していきたいと思います。
Haruka W.:私が最終的にめざしているのは、お客様も技術者も幸せにできるPMになることです。高品質なシステムを無理なく効率的に開発できる心理的安全性の高いチームづくりに貢献できる人材になりたいと考えています。これまで培った技術力を活かし、仕様の検討やPM補佐の活動にも挑戦しながら、貢献できる範囲を広げていきたいと思います。
Ayano M.:今回は総合テストの工程から配属されましたが、次のプロジェクトでは要件定義からシステム開発に携るため、開発を上流工程から理解しようと考えています。先輩方を見ているとそれぞれに強みがあるのを感じるため、私もITの専門でない立場を理解し、わかりやすいように通訳できるという強みを活かして、お客様とチームに貢献していきたいと思います。
※ 記載内容は2025年3月時点のものです