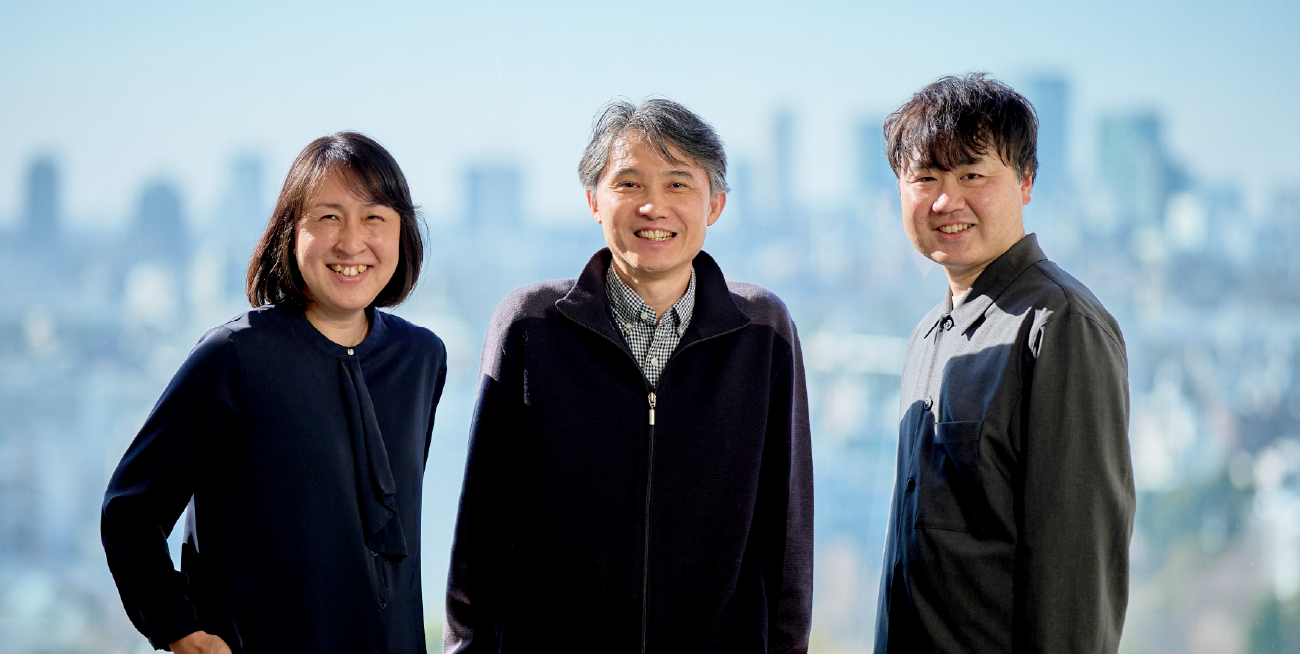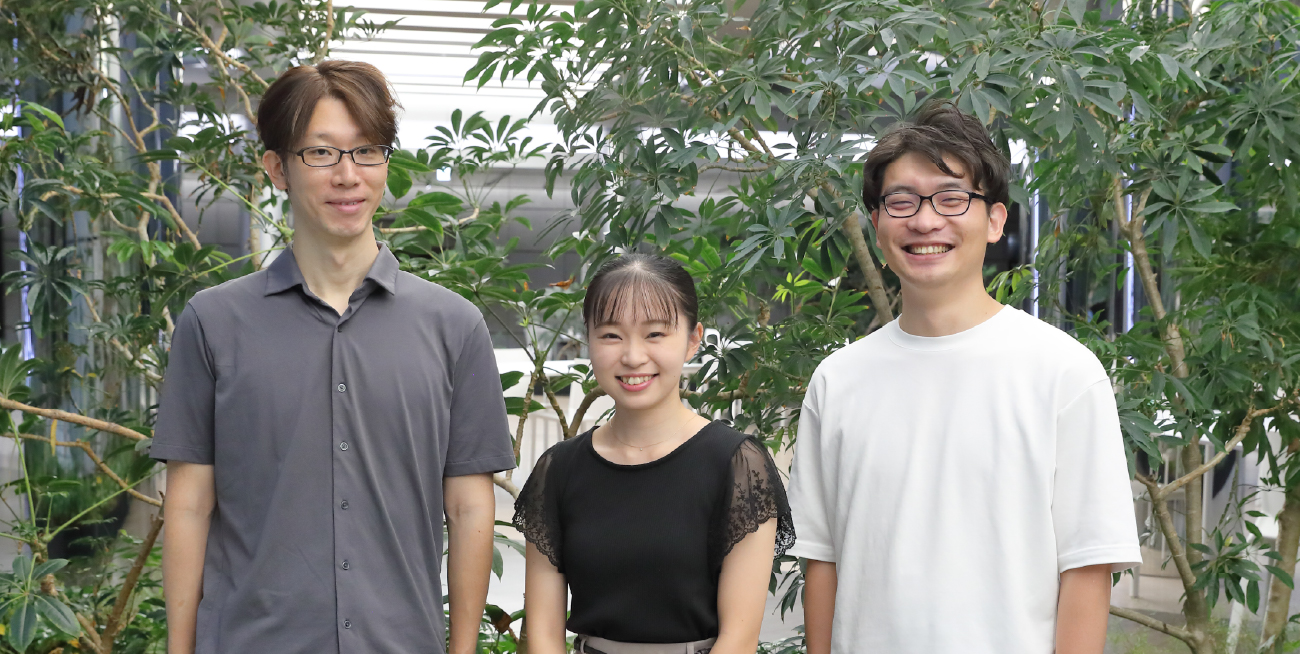医療や介護など、国民生活に直結する大規模システムの開発から運用保守を担うNECの第二官庁システム開発統括部。マネージャーを務めるTakeshi H.、社会保障領域に一貫して携わるJunko I.、キャリア入社で活躍するYuta F.の3人が、仕事のやりがいや魅力を語ります。
社会に貢献するために。強い想いと責任感を持ち、暮らしに直結するシステムを担う
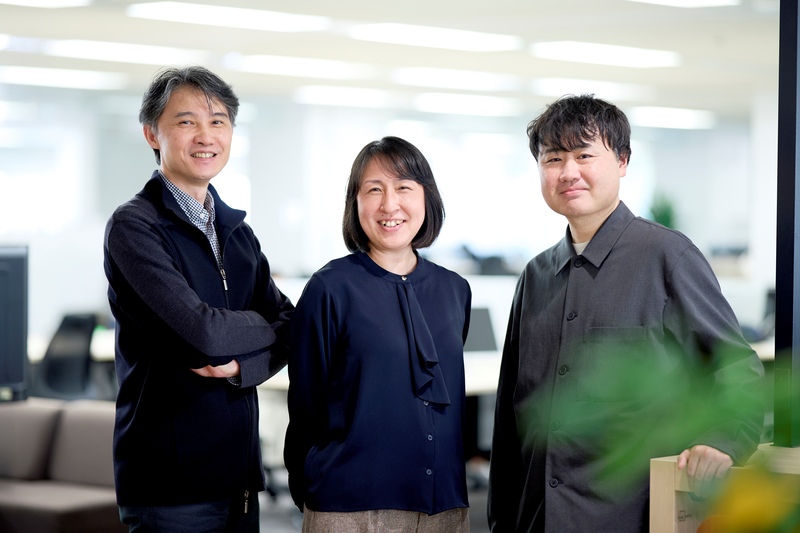
ICTソリューションの提供により、すべての世代が安心して暮らせる社会の実現をめざす第二官庁システム開発統括部。3人が所属する第三システムグループでは、主に厚生労働省関連の案件を担当しています。
Takeshi H.:私たちのグループでは、行政機関の間で行うマイナンバーの情報連携に必要なシステムや、医療・介護・健康に関わるシステムを手がけています。私自身はマネージャーとして、主にJunkoさんやYutaさんが手がけるプロジェクトの管理に取り組んでいます。
Junko I.:私が担当しているのは、原子力発電所で放射線作業に従事する方々の健康を管理するシステムです。プロジェクトリーダーとしてチームをまとめながら、システムの運用保守に従事しています。
Yuta F.:私は、ある自治体が薬の販売や許可などの情報管理に利用する薬事システムの運用保守を担当しています。ほかにも、厚生労働省が情報公開の請求状況を管理するシステムを担当しています。
安定した国民生活に欠かせない社会保障制度。その領域で20年以上システム開発に携わってきたJunkoは、仕事をする上で求められる資質についてこう話します。
Junko I.:一番大切なのは、社会をより良くしたいという想いです。私たちは、介護や子育てなど、誰もが身近に感じられる分野のシステムを支えています。人々の暮らしに貢献することにやりがいと責任を感じ、システムを止めないために納期と品質を徹底して追求する。そうした姿勢が求められると思います。
TakeshiとYutaも、「社会をより良くしたい」という想いで仕事と向き合っています。
Takeshi H.:私がNECに入社したのは、官庁や公共のエリアで大規模システムの構築に携わり、社会に貢献したいという強い想いがあったからです。第二官庁システム開発統括部で、医療や健康など人々の暮らしに直接関わるシステムの開発に携わり、入社当初にやりたかった仕事ができているという実感があります。
Yuta F.:2人が言うように、暮らしに身近なシステムだからこそ、絶対に止めてはいけないという使命感があります。とくに国の仕事は、法改正などでサービスの開始日が決まっているものが多く、納期は絶対に守らなければなりません。
プレッシャーも大きいですが、その分システムを通じて社会に貢献できていることに、大きなやりがいを感じます。
それぞれの経験を糧に。多様なバックグラウンドを活かしてたどり着いた現在のキャリア

第三システムグループに所属する以前は、それぞれ異なる経歴を歩んできた3人。Takeshiは1994年にNECへ新卒入社しました。
Takeshi H.:私は入社以来、約30年にわたって警察向けのシステムを担当してきました。たとえば、110番の通報時に警察官への出動要請を行うシステムの開発・運用保守などです。長く一つの分野で経験を積んできましたが、新たな分野に挑戦したいという想いが芽生え、3年前に現在の部署に異動しました。
プロジェクトの進め方自体は以前と変わらないため、これまで培ったマネジメントスキルが活かせています。しかしお客様との関係性やコミュニケーションの取り方は、部門ごとに異なるのだと気づきました。そのためお客様ごとの特性に合わせて、柔軟に対応する姿勢を大切にしています。
2002年に新卒入社したJunkoは、現在まで一貫して社会保障領域で経験を積んできました。
Junko I.:入社して最初に担当したのは、介護保険システムでした。全国47都道府県に展開する大規模なプロジェクトで、私は主にインフラ分野の企画・構築・保守を担当しました。そこで15年ほど経験を積み、2018年に厚生労働省の案件を担当する部署に異動しました。
その間、Junkoは仕事と育児の両立にも励んできました。
Junko I.:2010年と2013年に、それぞれ1年半ずつ育休を取得しました。当時から育休や時短勤務に関する制度は整っていましたが、現在はテレワークやコアタイムのないスーパーフレックスも導入されるなど、制度が一層充実化され、より柔軟な働き方が可能になっています。こうした制度と周囲のメンバーの理解に支えられ、仕事と育児を両立できています。
一方のYutaは、多彩なキャリアを経て2023年にNECへ入社しました。
Yuta F.:新卒入社した独立系SIerで約6年、お客様先に常駐してシステム開発に携わりました。その後、IT書籍の編集プロダクションで執筆・編集を数年経験し、Webフィルタリングシステムの会社でURLデータの収集・配信をするシステムの開発・保守を担当。
さまざまな業界のシステム開発を経験する中で、より社会的に重要なシステムに携わりたいという想いが強くなり、2023年にNECへキャリア入社しました。
実際に入社して感じたのは、人材の層の厚さです。たとえば、プロジェクトで人手が必要になった場合でも、すぐに増員が可能なことが印象的でした。私自身、去年は他のプロジェクトの応援に入る機会がありましたが、部署を超えた協力体制が整っていると感じます。こうした柔軟な人材の配置や組織横断でプロジェクトに参加できる環境は、前職にはなかった魅力だと思います。
DXの潮流とともに変革を推進──課題を乗り越え、お客様の要望に応えるシステムを導入

厚生労働省の幅広い案件を手がけている第二官庁システム開発統括部の第三システムグループ。中でもTakeshiは、障がい福祉サービスの請求・支払システムのプロジェクトが印象に残っていると話します。
Takeshi H.:ある自治体の障がい者支援を行う事業所向けに、サービス提供に伴う費用の請求・支払システムを導入するプロジェクトを担当しました。事業所がサービスの提供に関する申請を行うと、内容に応じた給付費が支給されるというシステムです。
当初はお客様だけでなく、システムのユーザーとなる事業所にも参加してもらう形でテストを計画していました。しかし調整が難航し、計画を変更せざるを得なくなったのです。残されたわずかな時間でお客様と集中的にテストを実施する必要があり、緊迫した状況が続きました。
そうした状況で私がマネージャーとして意識していたのは、状況を冷静に分析して対応することです。焦って感情的にならず、どうすれば納期に間に合わせられるかに集中して取り組みました。そしてシステムは無事にサービスインすることができ、現在は円滑に運用されています。さまざまな苦労があった分、達成感も大きく、システムを通じて社会に貢献できる喜びを実感しました。
Junkoは、システムのクラウド化に挑戦した経験が印象的だったと話します。
Junko I.:今から3年ほど前に、厚生労働省の案件でオンプレミスのサーバーからAWSへ移行するプロジェクトを担当しました。当時はまだAWSへの移行事例が少なかった時期です。
そのためノウハウを持つ有識者の知見も取り入れながら、試行錯誤して進めました。要件定義や設計について一つひとつお客様の合意を取り、品質と納期を常に意識して取り組めたことは、エンジニアとしての成長につながったと感じます。
AWSへの移行は、運用面にも大きな変化をもたらしました。
Junko I.:従来はメンテナンスを行う際に厚生労働省に出向く必要がありましたが、リモートで対応できるようになったのは大きな変化です。とくにコロナ禍においてはその効果が発揮されました。
また次期システムでは、デジタル庁の方針に従ってガバメントクラウドへの移行も予定されています。国の施策としてDXを推進できることが、この仕事の魅力だと感じます。
キャリア入社のYutaは、運用保守の現場で独自の取り組みを進めたことが印象深いと話します。
Yuta F.:業務に取り組む中で、プロジェクトの情報管理に苦労する場面がありました。そこで自主提案して始めたのが、情報管理の体制を改善する取り組みです。
これまでの作業ごとの手順書や問い合わせの記録データはしっかり保管されていたのですが、それらを効率的に検索・活用できる仕組みは整備されていませんでした。そのため新たなツールを導入し、必要な情報へのアクセス性を高める仕組みづくりに昨年から取り組み、運用を推進しています。
こうしてキャリア入社ということを意識することなく積極的に提案ができるのは、年齢や社歴にかかわらず意見を受け入れてもらえる風土がNECにはあるからです。提案の根拠や効果を明確に示せば採用してもらえるので、自ら課題を見つけて挑戦するモチベーションにつながっています。
最新の技術とチームの力を活かして──時代の変化に合わせ、システムを進化させていく

さまざまな経験を糧に、安全で安心な暮らしを支えるより良いシステムの開発をめざす3人。今後の展望について、Takeshiはこう語ります。
Takeshi H.:社会に貢献したいという入社当時からの想いを変わらず持ち続け、これからもお客様の要望に応える高品質なシステムを追求していきたいと考えています。今まではオンプレミスの対応が中心でしたが、社会保障の領域においてもクラウド化が進んできました。
今後はこうした機会がさらに増えると思うので、クラウドに関する知見を深めていきたいと思います。
またマネージャ―としては、組織体制の改善にも取り組みたいと話します。
Takeshi H.:現在は、プロジェクトでアサインされるメンバーが一部固定化されている業務があるのですが、属人化を解消し、より柔軟なチーム運営を実現することが目標です。ある程度の期間で担当を入れ替え、誰でもプロジェクトに対応できる体制の構築をめざして取り組みを進めています。
Takeshiと同じく、属人化を解消するためノウハウの共有を強化していきたいと語るJunko。さらに、これまでの経験を活かした新たな価値の創造も見据えています。
Junko I.:AWS環境での構築・運用の経験を活かしながら、次に見据えているガバメントクラウドへの移行というテーマに挑戦していきたいと思います。そこで新たな知見を磨き、厚生労働省の案件にとどまらず、他のプロジェクトにも展開していきたいですね。
プロジェクト間の情報交換を積極的に行い、最新の技術も取り入れながら、より効率的で高品質なシステムの開発や運用保守につなげていきたいと思います。
Yutaは、新たな技術への挑戦を思い描いています。
Yuta F.:現在担当しているシステムは、数年後に大規模な更改を控えていて、次期システムはクラウドで構築することになります。前職でのAWSを使った開発経験と新たな技術を活かし、クラウドネイティブなアプリケーションの開発に挑戦することが目標です。そしてお客様の要望にお応えする、より良いシステムを追求していきたいと考えています。
クラウドへの対応など、変化を続ける社会保障システムの領域。これから未来を担う人材に求められる資質について、3人が語ります。
Takeshi H.:やはり社会に役立つシステムを開発したいという強い想いを持っている方が向いていると思います。統括部にはそうした人材が集まっていて、横のつながりも強く、若手が多くて活気にあふれた雰囲気です。わからないことがあればすぐに相談できる環境があり、サポート体制も充実しています。
また、NECが手がけている案件の幅はとても広いので、さまざまな経験を積んでキャリアの可能性を広げたい方には最適な環境です。
Junko I.:大規模なプロジェクトが多いので、みんなで一つの目標に向かい、お客様と一緒に考えながら進めていくことに楽しさを感じられる人が向いていると思います。私たちの統括部はとてもチームワークが良く、仲間と協力し合える安心感があります。
自分がやりたい仕事やめざすキャリアについても、相談しやすい環境です。年齢や社歴を気にせず意見を言い合えるので、私自身も若手のメンバーに大きな刺激を受けています。
Yuta F.:今はちょうど、従来型のシステムからクラウドネイティブな構成への移行期です。新しい技術に挑戦したい方にとっては、そうしたプロジェクトに携われる大きなチャンスだと思います。NECには手を挙げた人に裁量を与える風土があるので、自分で考えてより良いものを追求したい方には理想的な職場です。
そして若手に任せても放任するのではなく、壁にぶつかったらしっかりサポートしてもらえるので、安心して自分のやりたいことに挑戦してほしいと思います。
※ 記載内容は2025年2月時点のものです